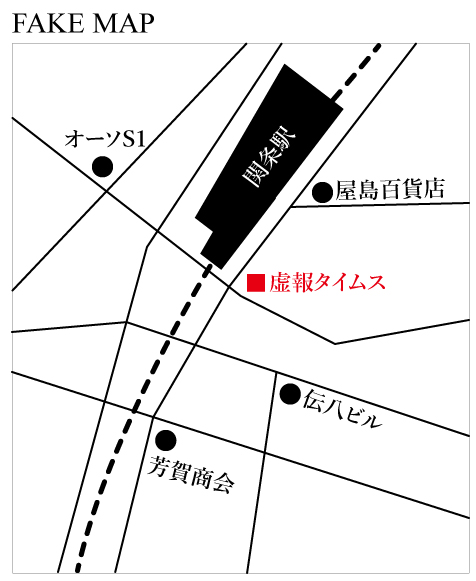「幻の映画作品」75年ぶり発見 カンヌで上映へ
シュールレアリズムの巨匠として活躍した画家、フリードリヒ・アプフェルバウム(オランダ)※1の「幻の映画作品」、『男、来る』(1929年)が今月、75年ぶりにスペインで発見された。
これは、サルバドール・ダリの『アンダルシアの犬』※2に触発されたアプフェルバウムが、生涯で唯一映画製作に携わったもの。脚本から監督、出演まで全て一人でこなしている。「傑作」「問題作」と反響を呼んだものの公開は一部の映画館だけに留まり、1930年の上映を最後にフィルムの行方はわからなくなっていた。
現在開催中のカンヌ国際映画祭で上映予定。
フィルムは、スペインの映画プロデューサーの男性が所有。「代々引き継いだ」と語るこのペドロ・タマリッツ氏の祖父は、「スペインの花」と呼ばれた美術家ペドロ・クワンケである。クワンケは、『男、来る』を公開当時に観た数少ない人物の一人。また、アプフェルバウムとの親交が厚く、フィルムを譲り受けたとみられる。
このような経緯が世界的に注目を浴びたのは、今月10日。しかし、今注目されているのはこの映画の内容である。
モノクロ製のこの映画は、机の上の甲虫(カメムシ?)のアップから始まる。すると、画面に指が一本侵入し、これを押しつぶす。机には体液が飛び散るこのシーンは意味深で不気味だ。
その他、畑に生っているかぼちゃが突然割れて、中から真っ白なタイツ(?)に身を包んだ人物が登場するなど、不気味すぎて狂気を感じる出来。ずっとモノクロ、サイレントというのも効果を挙げている。シュールな映像と抽象的なイメージ、明確なストーリーは見当たらないなど、『アンダルシアの犬』を意識して作られたとは納得の内容である。
このような、シュールレアリズム画家の脳内を現実に移した様な場面の後、画面は屋内から玄関ドアを映し出す。すると突然ドアが開き、黒尽くめの男(アプフェルバウム本人)が登場。この男は、画面を見据えて、なんと言葉を発する。今までサイレント映画だと思って観ていた観客が驚くのはこの瞬間である。男は、画面=観客に向かって一言だけ話すと、再びドアを開けて外へ出て行く。そして、画面には「END」の文字。全27分。
当時導入されたばかりのトーキーを利用し、観客がサイレントと思い込んでいる最後の最後で発せられる「一言」、そしてその一言の衝撃は当時の欧州で賛否両論を呼んだという。アガサ・クリスティーの『アクロイド殺し』にも似たこの結末は、画期的な試みだった。
上映時間27分の中、唯一の音であるこの「最後に発せられる一言」は、『それまでの不気味な映像の理由を明らかに』(脚本ト書きより)するもので、この作品を「幻の映画作品」たらしめる理由でもある。
このフィルムは、5月20日にカンヌ国際映画祭にて上映予定。完成から75年以上経った今、再び世界で賛否両論が起こると予想する評論家は多い。
- 「衝撃度は計り知れない」(マイク・パーク:評論家)
- 「この作品に出会えて幸せ」(おすぎ:評論家)
- 「全仏が泣いた」(パリ・ドゥヨン・ニューデル紙)
- 「全伊が感動」(イタリー・ミラ・コテツォッラ)
- 「全米が震撼」(ニューヨーク・タイム紙)
- 「国民総驚愕必至的事実」(中華新電事報紙)
一番重要な、来る男の「一言」。来年予定されている一般公開にて、御自分の耳で確認を…。