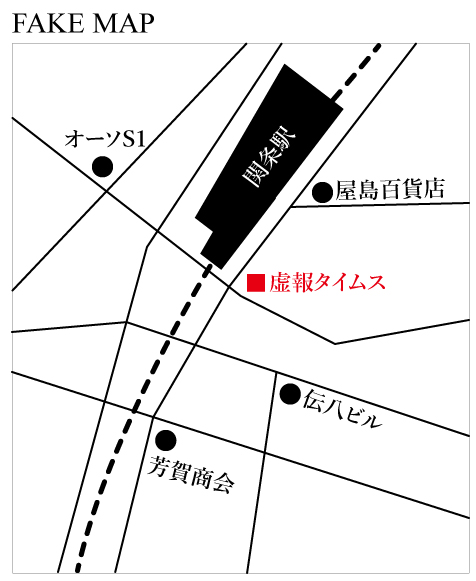BAR “A SIN HE”
私のイギリス旅行の最後は、とあるバーだった。
ロンドンのウェルリバー通り―19世紀には下級労働者のたまり場だったと説明を受けたこの場所も、100年後は市民の行き交う大通りだった―に立ち並ぶ、多くの酒屋。そんな場所に構えるバーも珍しいが、ガイドによれば「とっておき」の店らしい。
案内のままに連れられて店の前に立つと、消えそうに点滅するネオンでBAR “A SIN HE”と看板が見える。 奇妙な名前だが、何かの熟語なのだろうか。”SIN”は「神に反する」…。「神に反する彼」? それに、玄関扉の”NO ENTRY WOMAN”の文字が真っ赤に目立つ。
しっくりこない感覚を抱えたまま一歩店内へ足を踏み入れると、そんなもやもやを吹き飛ばす飛び切り爽快な香りが刺激してきた。 イギリスのバーには珍しい、赤いビロード風の床材が気持ちいい。私が期待した棚一杯のボトルは無かったが、不思議とバーの雰囲気は痛いほど感じる。オレンジがかかった灯りは、夜気で冷えた身体を暖めてくれるような気分にさせる。
カウンターへ座ると、タイミングよく老人が現れた。白人にしては、いや日本人にとっても相当小柄な老人だった。灰色の肌と深紅の唇が目立つ彼は、私のイメージしたスマートなバーテンダーとはかけ離れた印象だったが、正装はしている。ガイドは彼が店主だと説明してくれた。
私は、香りの原因であろう酒を注文したくてうずうずしていた。爽快感は今や一種の焦燥感に変わり、咽喉は枯れ、鼻腔はちくちくとしている。
「香りの原因をくれ」、そう伝えると、店主は棚に一本だけ並ぶボトルを持ち上げた。よく見ると、店内のあちこちに置いてあるボトルは全てこれと同じのようだ。
枝のような老人の腕で栓が開けられた瞬間、香りはいっそう強まった。どこからか取り出されたグラスを私が受け取ると、透き通った緑色の液体が注がれる…。
私は、手が震えていることに気が付いた。店内は、静まり返っていることも、緊張させる原因だろう。ガイドはいつの間にかいなくなり、店主の老人は緑色に濁ったような眼でこちらを見つめていた。
香りを十分に嗅いだおかげで、鼻腔は干潟のような状態から満潮へ変化した。 口を開けると、液体は、そろりそろりと浸入を開始する。強烈な苦味と同時に、香りが吹き抜ける感覚 ―初めて酒を飲んだときのような―。
私は一気にそれを飲み干すと、きらめくグラスを無言のまま店主に差し出した。
目覚めたとき、最初に見えたのは真っ青な天井だった。
どうやら横たわっているらしい私の周りには、たくさんの男が見える。彼らは全員白い服に身を包んでいた。身動きをとろうとしたが、頭に空気が溜まったような感覚。何かが巻かれてる感じがして、妙に身体も重い。いざというときのために昔から習っていた空手も、こんな場合は役に立たない。
東洋人が、日本語で言った。 「目が覚めましたか。我々は医師団です。あなたに、衝撃的なことを伝えなくてはなりません。大丈夫ですね。あなたが倒れているのが発見されてから、ずっとこん睡状態でした」 私は、倒れていたのか。記憶がよみがえる。そうか、”Bar A SIN HE”で酒を飲んで ―。
「いいですか、落ち着いてくださいね。現在の日付は2035年です。30年間、あなたはツヨンの多量摂取でこん睡状態だったのです。一体、30年前何があったのですか?」 私が旅行したのは、2005年だ。30年間も眠っていた、と? そんな、そんな―…。
話し終わった東洋人の後ろに、緑に濁ったビー玉のような眼と鋭い頬骨、灰色の肌の中で目立つ紅色の唇の骸骨のような顔が見えた。それが、窓ガラスに映った私だと判断できるまで、1秒とかからなかった。 私の30年間は、1秒で過ぎ去ったのだ。
30年前。男が倒れた夜、バーのネオンが点滅した。消えていた”B”と”T”が点いたとき、 “Bar A SIN HE”は、”Bar ABSINTHE”になっていた。 今日もまた、魔酒ABSINTHEは誰かの口に入る…。